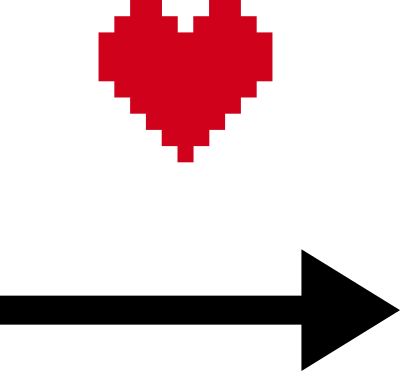・寄付金は、プロジェクト終了の翌月か12月中旬のいずれか早い方に活動団体へ寄付致します。
能登半島地震被災地復興支援
https://lp.aarjapan.gr.jp/noto_eq
-
- TOTAL
- ¥
- 452,093
AARは、紛争や災害など自分ではどうすることもできない理由で困難に直面しながら生きる人々を支えます。
気持ちだけですが。トルコは親日でとても美しい国ですよね。少しでも役立ちたいです。
→
AARさん、能登でも現地での活躍を期待しています。頑張ってください!
スポンサーに参加しました。
スポンサーに参加しました。
スポンサーに参加しました。
寄付しました
活動報告
AARは、能登半島地震の被災地、石川県七尾市と、同市内の福祉事業所と協力して、障がいのある方も利用できるトイレやシャワーを完備した「福祉避難所」の設置を支援しました。2026年1月29日、現地で内覧会が行われました。
設備が完成したのは、障がい者の就労支援を行っている一般社団法人ななお・なかのと就労支援センター(七尾市、瀧川嘉明・代表理事)が運営する就労継続支援(A型)事業所「LABO」(同市白馬町)です。
「長期間の避難生活に耐えられるよう、シャワールームもあります」。センター長の木谷昌平さんは話します。
設備が完成したのは、障がい者の就労支援を行っている一般社団法人ななお・なかのと就労支援センター(七尾市、瀧川嘉明・代表理事)が運営する就労継続支援(A型)事業所「LABO」(同市白馬町)です。
「長期間の避難生活に耐えられるよう、シャワールームもあります」。センター長の木谷昌平さんは話します。
周囲を気遣い、自宅避難を続ける方も
能登半島地震の発生直後、多くの住民が体育館や公民館などの避難所に避難しました。その一方で、発達障がい者や知的障がい者の中には、避難所における環境の変化等により状態が不安定になる人もおり、家族らが遠慮して倒壊の恐れのある自宅に留まったり、車中泊を続けたりするケースが多数見られました。その結果、災害関連死につながりかねない、障がい者本人や家族の健康状態が悪化する事例が発生しました。
このためAARは、障がいのある方が安心して利用できる福祉避難所の整備を支援しています。このたび、福祉避難所の体制強化を進める七尾市と、ななお・なかのと就労支援センターとの間で協定が結ばれ、「LABO」を災害時に「福祉避難所」として利用することが決まりました。
AARは、災害時に寝泊まりができるよう、作業場の床をフローリングに張り替え、シャワー室、バリアフリートイレやキッチンを整備しました。整備費用の総額647万円は、AARにお寄せいただいた寄付金で賄われました。
この事例は、「行政との協定」と「民間(NPO)の支援」を組み合わせることで理想的な避難環境を早期に実現した先進的な取り組みと言え、災害関連死を防ぐための具体的な解決策として広がりが期待されています。AARは、今後もこうした被災地復興の取り組みを支援していきます。
レポートはこちらからもご覧いただけます。
https://aarjapan.gr.jp/report/21007/
写真左:AARの支援によって整備されたバリアフリートイレ
写真中央:入口に段差がなく車いすでも入りやすいシャワールーム
写真右:内覧会で、福祉避難所として整備された作業所内部を案内する木谷昌平さん(左)
(2026年1月29日、石川県七尾市就労継続支援(A型)事業所「LABO」)
能登半島地震から2年。被災地では、今も多くの被災住民が生活再建の途上にあります。とりわけ障がいのある方々は孤立しやすく、支援の網からこぼれやすい状況に陥ります。そうした方々の「困りごと」に寄り添う個別支援を続けています。
「通院が難しい」「地震で散らかった部屋を片づけたい」
発災直後からAARと協力して支援を行ってきた障がい者団体の日本障がいフォーラム(JDF)の「JDF能登半島地震支援センター」(七尾市)には日々、障がい者やその家族からさまざまな相談が寄せられます。AARはJDFや地域のNPOと協力し、病院や福祉施設への送迎、家屋の応急処置、行政窓口での被災者支援制度の申請サポートなど、2025年12月1日までに93件の相談に対応してきました。
「困っているのはやっぱり食事かな。ヘルパーさんが来ない日は、近くのコンビニだけしか行けず、食事が偏ってしまう。」
そう話すのは、ダウン症の娘(35歳)と暮らす視覚障がいのある男性(77歳)です。AARはこの親子に対し、病院やショートステイへの送迎、買い物や提携電話の手続きの付き添いなど、日常の小さな困りごとを継続してサポートしています。親子をよく知るマッサージ師の女性は「近所の助け合いだけでは難しい部分をAARが担ってくれて、本当に助かっています」とはなします。
行政の支援制度は手続きが複雑で、障がいのある方には活用が難しいこともあります。知的障がいのある男性と自閉症の息子の世帯で、地震で浴室は破損しました。AAR職員は男性とともに市役所に行き、応急修理制度の申請をサポートしました。被災状況の撮影や業者への見積もり依頼も代行し、無事に浴室を修繕することができました。
また、障がいや高齢のために自力で作業が難しい被災者の家屋に対しては、連携団体と協力して修繕作業も支援しています。
AARは、一部損壊のため補助がほとんど受けられず、自宅を修繕できずにいる高齢の要配慮者のご夫婦がいらっしゃると、志賀町役場から紹介を受けました。AARと連携団体は、このご夫婦の自宅の修繕を実施しました。ご夫婦は、「(寝室の)壁などが落ちてくるのではないかと心配していましたが、安心して眠れるようになりました」と話しています。
AAR能登事務所の栁町浩平は「障がいのある方々と接していると、買い物や家事、洗濯など、多くの場面で手助けが必要だと感じます。そうした日常の困りごとにも目を向けながら、今後も伴走し続けたい」と話します。
AARは被災地で障がいのある方々に暮らしに寄り添い、必要な支援を届けてまいります。加えて、被災地の地域コミュニティーの維持や活性化、外国人被災者支援を実施し、誰も取り残さない復興を支援します。今後もAARの能登半島地震被災者支援にご協力のほどよろしくお願いいたします。
写真左:高齢のため自力での作業が難しい被災者の家屋の修繕作業を行う連携団体「風組関東」のスタッフ(2025年10月25日、石川県志賀町)
写真右:ショートステイへの送迎をするAAR能登事務所の栁町幸平(右)(2025年12月1日、石川県中能登町)
能登半島地震から1年9カ月、奥能登豪雨から1年がたちます。被災地の障がい者施設では、利用者が少しでも日常を取り戻せるよう、職員の方々が懸命に活動を続けてきました。AARは2025年9月上旬、そうした支援を行う職員の方などをサポートすることを目的とした研修会を開催しました。
1年9カ月間の苦労を共有
研修会は2025年9月6日、七尾市和倉地区で開催され、同市と石川県内の7つの福祉事業所から24人、さらに輪島市と能登町の福祉担当職員2人が参加しました。自分の中に抱え込みがちな苦労や日々の課題を共有することで気持ちを軽くしてもらうこと、また、セルフケアの方法を身に付けてもらうことが目的です。
輪島市中心部で、障がい者向けグループホームなどを営業している「輪島カブーレ」は震災後、被災者が少しでも心身を休められるよう、市役所内で運営委託を受けていたカフェスペースを避難所として活用しました。また、運営する温浴施設を2025年1月12日に再開し、地域住民の憩いの場として提供しました。
輪島カブーレで相談支援専門員を務める田端未央子さんは、「地震以降、少しでも早く元の生活に戻れるようにずっと努力してきて、そこに奥能登豪雨も発生した時は、心が折れそうになった。それでも、多くのボランティアの皆さんが活動している姿を見て、前向きな気持ちになりました」と大変な中でも励まされた経験を共有しました。
障害者就労支援事業所を運営する「奥能登WORKSスタジオ」は、能登半島地震で集落のインフラが寸断され地域が孤立したため、備蓄していた食料や水を地域住民に提供しました。その後、住民がヘリコプターで金沢市へ二次避難していく中、事業所では「地域の人がまた戻って来られる場所をつくろう」との思いで、地震前から営業していたカフェスペースの片付けを始めました。家安祐美さんは「地震後は人手不足の中で事業が増え大変だった」と振り返りながらも、「地域の人々や県外から訪れる業者、観光客とのつながりを得られたことは良かった」とプラス面もあったことを強調しました。
支援者自身も支援を受けてよい
能登総合病院の臨床心理士・寺井真奈美さんからは、「体と心のケア」をテーマに、実践的なセルフケア法について話していただきました。
寺井さんは、「被災地での支援は、常に気を張っている時間が長く、心のブレーキが効かない。考え方を変えるだけで楽になることあるので、悪い方に考えすぎないようにプラス思考でいることが大事」と語りました。「疲れていることを自覚し、意識的にリセットすることが大切」と話し、実践的なセルフケア法として、リラックスするための呼吸法などを紹介しました。
福祉関係者などの「支援者」は、災害時、自分のことを後回しにしがちで、その結果、精神的・肉体的に疲弊してしまうことが少なくありません。周囲の人が「休みましょう」と声をかけること、「支援者も支援されて良い」という考えを広めていくことが大切だと改めて感じました。AARは、今後も能登半島地震被災地での活動を続けてまいります。今後ともご支援をお願いいたします。
レポートはこちらからもご覧いただけます。
https://aarjapan.gr.jp/report/20026/
写真:研修会で支援経験を共有する参加者の皆さん(2025年9月6日 石川県七尾市)
能登半島地震で被災した石川県輪島市町野地区に7月7日、臨時災害放送局「まちのラジオ」が開局しました。AARは、ラジオ放送の拠点となるコンテナハウスを支援し、「まちのラジオ」が、町野町の皆さんの声を届け、人の輪をつなぐラジオ局となるようサポートしています。
「臨時災害放送局」は、大規模災害の際の被害軽減を目的とし、地域と期間を限定して設置されるラジオ局です。インフラの復旧情報や、行政からのお知らせ、地域で行われる催しなどの情報を発信します。まちのラジオでは、そ町民をゲストに迎えたり、メッセージやリクエスト音楽を届けたりと、交流の場としての役割も担います。「町野町復興プロジェクト」(山下祐介代表)がクラウドファンディングで開業資金を集め、10人のボランティアが、パーソナリティも含めた運営を担っています。
放送を開始した7月7日には開局式が行われ、多くの報道陣も集まりました。また、9日にはAAR職員も電話で生出演し、能登での支援活動についてお話ししました。
AARは2011年、東日本大震災で被災した宮城県女川町で、臨時災害放送局「女川さいがいFM」にコンテナハウスを提供し、開局を支援しました。同局は、一般社団法人「オナガワエフエム」として、ラジオ番組の制作や、全国の被災地で臨時災害放送局の開局をサポートする活動を現在も行っています。
一方、「町野町復興プロジェクト」は、町民交流イベントの開催や、ボランティアセンターの運営をしていましたが、住民向けの情報発信がインターネットを使った発信に集約され、特に高齢者や、電波の悪い山間部でアクセスしづらいことが課題でした。
そこで、町野町復興プロジェクトの山下代表がオナガワエフエムに相談し、災害FMの開局準備が始まりました。しかし、放送の拠点となる場所がなかったため、AARに相談があり、6月16日にコンテナハウスを設置しました。AARは「まちのラジオ」が地域の声の拠点として育ち、町野の復興を支える存在になることを願い、サポートしていきます。
能登半島地震の発生から1年半が経ち、AARはさまざまな団体と協働しながら復興に向けた活動を続けています。特に障がい者支援においては、地域の福祉施設や作業所に加え、障がい者支援のNPO法人やネットワーク組織とも連携して支援活動を進めています。
障がい者団体の連携組織である日本障害フォーラム(JDF)とAARは、障がい福祉事業所の復旧支援や障がいのある方の病院への送迎支援、視覚障がい者への支援などを連携して行っています。また、両者で情報を共有して、JDFが福祉制度に関する相談を担い、AARが家屋の応急処置を行うなど、それぞれの得意分野を活かして対応するケースもあります。
今回、JDF能登半島地震支援センターでスタッフマネージャーを務める大野健志さんに、AARとの協働についてお話を伺いました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AARさんと私(大野健志さん)が、初めて一緒に活動したのは、東日本大震災の時です。宮城県南三陸町の障がい者の福祉作業所が津波の被害を受けたのですが、高台に仮設のプレハブを建てる支援を手伝ってくれました。付き合いは長いのですが、能登支援で深く協働するようになって、しっかりとした理念を持った人道支援団体なんだと、AARの見方が変わりました。
震災直後、私たちはどこの施設が被災したかという情報は持っているのに、必要な支援を届けるマンパワーも資金も不足していました。そのような状況でAARとつながれたことは心強かったです。特に、震災から2日後の1月3日に珠洲市の障がい者事業所に支援物資を届けてくれた時は本当にありがたかった。
JDFは障がい者支援を専門とする組織であって、災害時の緊急支援のプロではありません。国内外で多くの緊急支援の実績があるAARさんと協働できることは、私たちにとって意義深いことです。
AARとの協働として一番印象に残っているのは、昨年9月の能登大雨の時です。聴覚障がいのある方が多く利用する能登町にある福祉作業所が、氾濫した河川からほど近いこともあり、浸水被害に遭って備品などが使えなくなりました。施設の職員の方も被災したため、JDFは職員に代わって利用者さんをサポートする人的支援に回りました。AARは、備品や什器をすぐに手配してくれました。地震に続いて大雨の被害を受けたのは本当に気の毒でしたが、普段からAARと連携していたことで、迅速な対応ができたと思っています。
被災した人々と話していると、みんな我慢している、ということをよく感じます。ある程度信頼を深めてからでないと本音を話してくれません。その点、障がい者の方や施設の職員の方と直接話す機会が多い私たちの方が、今どのようなことで困っているのか、ニーズを拾いやすい立場にあります。
そうして得られた課題をAARと共有して、どのような支援ができるかを一緒に考え、実施しています。今後も、きめ細やかな支援を一緒に続けて行きたいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
震災から1年半が経過した今も、被災地では復興に向けた課題が山積みとなって残されています。AARは、復旧できていない障がい福祉事業所への支援や、生活再建が進んでいない障がい者への支援など、誰一人取り残さない復興に向けた活動をJDFなどの団体と連携して続けてまいります。引き続きご支援くださいますよう、お願い申し上げます。